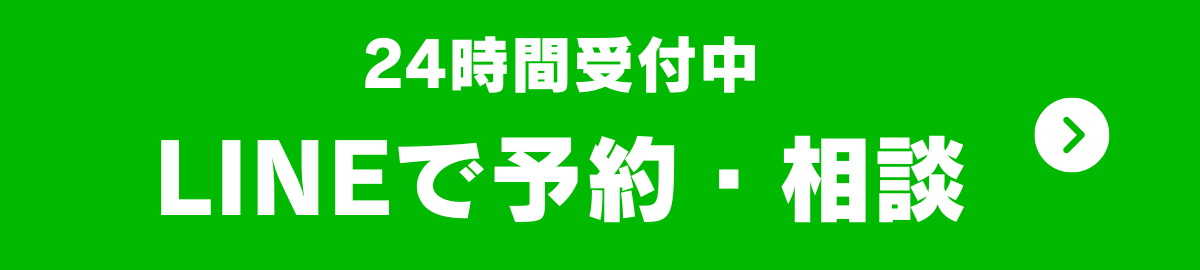被爆二世として思う8月6日 ― 湯崎知事の平和記念式典メッセージと核抑止論への考察

8月6日と8月9日 ― 核のない未来へつなぐために
私は広島市に生まれ育ちました。
夏を迎えると、8月6日と8月9日はどうしても心に浮かびます。
広島と長崎に原子爆弾が投下された日――人類史上初めて核兵器が使用され、大惨事となった日だからです。私は被爆二世にあたります。
父は当時、福山市に疎開していました。実家は広島市荒神町にあり、終戦後、広島へ戻ってきたそうです。広島が被爆してからおよそ2週間後のことでした。そこまでは父の口から聞きましたが、そのとき街がどうなっていたのかは、一切語ってくれませんでした。
私の叔母二人は、爆心地からおよそ3キロの実家で被爆しました。中学生の頃、授業で「平和学習」というプログラムがあり、被爆体験者に話を聞くという課題がありました。現実をよく知るはずの叔母に話を聞こうと思い、訪ねました。
しかし二人とも口を閉ざし、何も語ってくれませんでした。普段は明るく話好きな人たちなのに、そのときは急に表情が曇り、沈黙が流れました。私は当時、不思議でなりませんでした。
年月を重ね、なぜ語ってくれなかったのか、少しずつ分かるようになってきました。
私はこれまで、阪神・淡路大震災や東日本大震災を経験し、被災した方々が当時のことを語りたがらない姿を見てきました。おそらく、目の前であまりにも多くの死や地獄のような光景を見たとき、それを思い出すだけで言葉を失ってしまうのだと感じます。
だからこそ、叔母が沈黙した気持ちも理解できるようになったのです。
今、被爆を生き延びた方々は残りわずかになりました。それでもなお、語り部として勇気をもって後世に伝えてくださる方がいます。本当に尊いことです。私は直接の被爆者ではないため、いくら想像しても実感には限界があります。それでも、今語ってくださる人たちの声に耳を傾け、資料を見て学び続けたいと思います。戦争を知らない世代がつなげていかなければ、同じ過ちを繰り返す危険があると感じるからです。
今年8月6日の平和記念式典で、広島県の湯崎知事が述べられた挨拶の中で、心に残った部分があります。以下に抜粋します。
草木も生えぬと言われた75年からはや5年、被爆から3代目の駅の開業など広島の街は大きく変わり、世界から観光客が押し寄せ、平和と繁栄を謳歌しています。しかし同時に、法と外交を基軸とする国際秩序は様変わりし、剥き出しの暴力が支配する世界へと変わりつつあり、私達は今、この繁栄が如何に脆弱なものであるかを痛感しています。
このような世の中だからこそ、核抑止が益々重要だと声高に叫ぶ人達がいます。しかし本当にそうなのでしょうか。歴史が証明するように、ペロポネソス戦争以来、力の均衡による抑止は繰り返し破られてきました。なぜなら抑止とは、あくまで頭の中で構成された概念、つまりフィクションであり、普遍の物理的真理ではないからです。
自信過剰な指導者の出現、突出したエゴ、民衆の高揚、誤解や錯誤により抑止は破られてきました。我が国も、力の均衡では不利と知りながらも太平洋戦争を始めたように、合理的判断が常に働くとは限らないことを身をもって示しています。
実際、核抑止も80年間無事に守られたわけではなく、核兵器使用の危機に直面した事例も歴史に記録されています。
私はかつて、核抑止論に一定の理解を示したこともありました。
しかし、ロシア・ウクライナ戦争やパレスチナ・イスラエル紛争の報道に触れるたび、核兵器が“脅し”として使われる現実を目の当たりにします。存在する限り、いつか使われる日が来る――そう思うと、核抑止に頼る考え方は危ういと感じます。
この点で、湯崎知事のメッセージに深く共感しています。
核兵器は、使われないために存在していても、その存在自体が人類の未来に暗い影を落とします。だからこそ、なくすための努力をやめてはいけない。8月6日と8月9日を忘れず、次の世代へ真実と願いを手渡していきたいと思います。