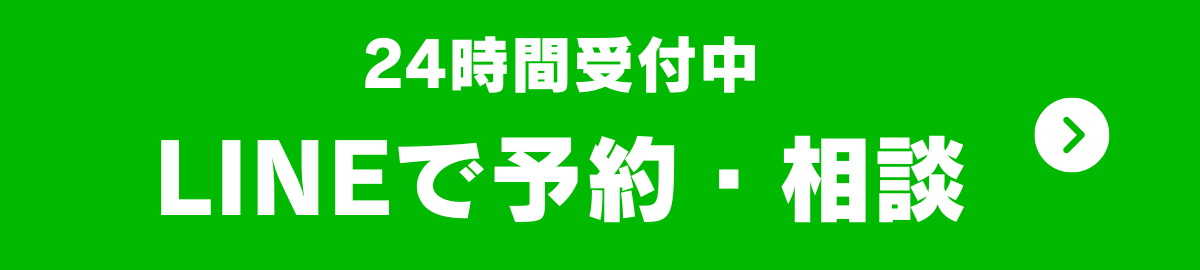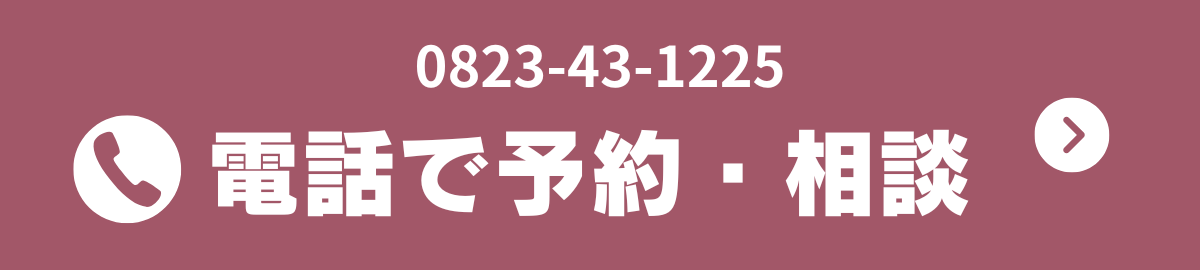自律神経無痛療法とは
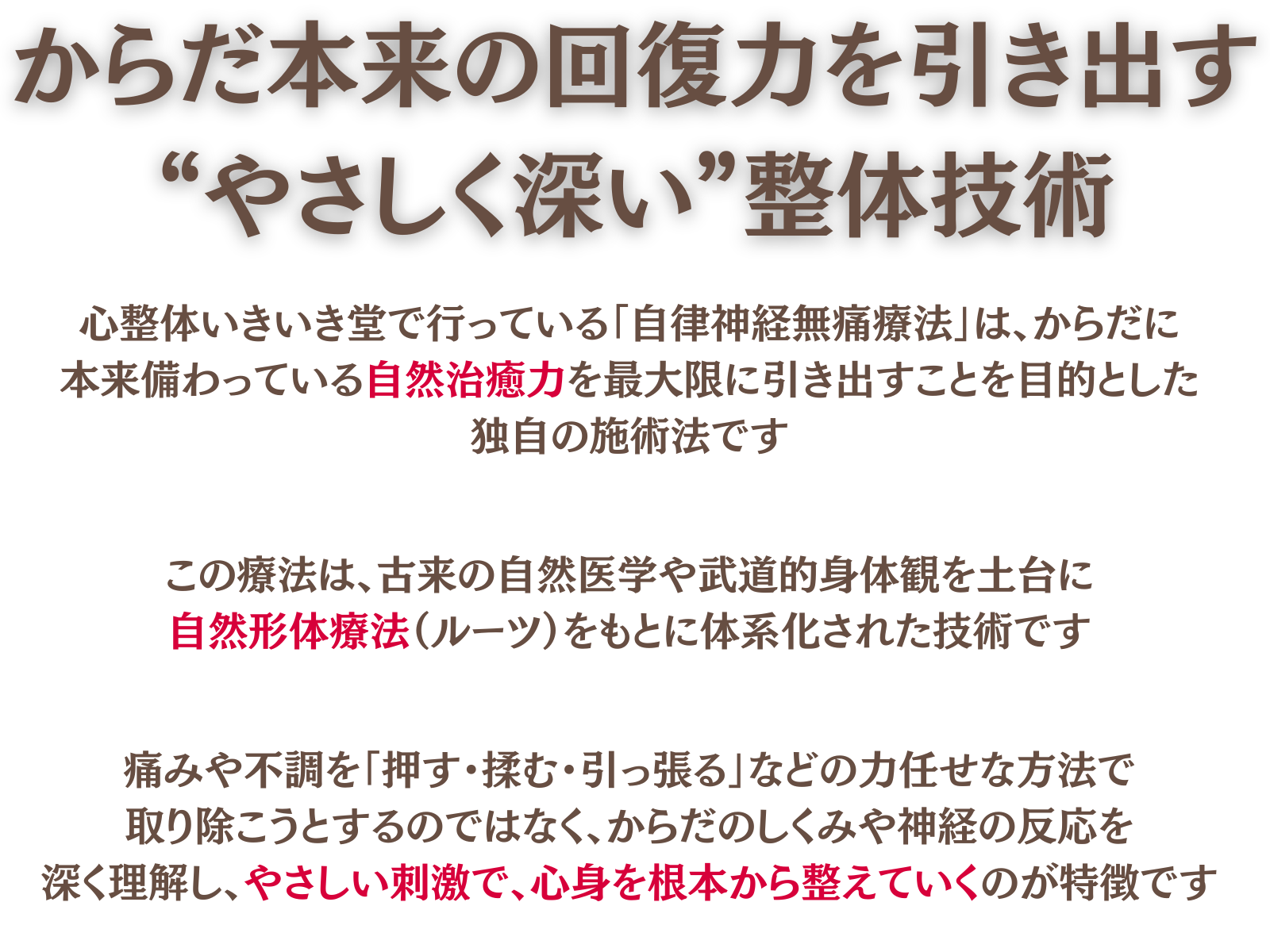
特徴と考え方
❶身体の「防御反応」を解除する
人の身体は、危険を感じると無意識に身を守ろうと緊張します。
この緊張が続くと筋肉が硬くなり、血流が滞り、痛みや不調につながります。
無痛療法では、呼吸・姿勢・動きの方向などを丁寧に見極め、身体が「これは安全だ」と感じて自然にゆるむよう促します。
❷神経と筋肉の”反応”を利用する
筋肉は引っ張られると反射的にゆるむ性質があります。さらに「吐く息(呼気)」と合わせて行うと、より深いリラックス反応が得られます。
こうした神経の性質を応用し、無理のない動作で全身のバランスを整えていきます。
❸「痛みのない方向」に導く
無理な動きや痛みを伴う刺激は、身体をさらに緊張させてしまいます。
当院では、痛みの出ない方向を見つけ、そちらに誘導することで、身体の安心感を引き出し、自然に動きを取り戻します。
❹身体は「治りたがっている」
人間の身体は、何もしなくても傷を治し、骨をくっつけ、炎症を抑える力を持っています。
この力を妨げず、むしろ最大限に発揮させることが、本当の改善の目的です。
そのため、強く押したり揉んだりするような刺激は逆効果になりかねません。
❺やさしく、でも”科学的”
無痛療法は単なる「癒し」ではありません。
神経の反射・筋肉の性質・呼吸と自律神経の関係など、からだのしくみに基づいて開発された科学的かつ再現性のある施術法です。
最後に
不調や痛みは、からだからの「メッセージ」
薬で消すのではなく、その声に耳を傾け、根本的な原因と向き合うことが必要です。
当院の自律神経無痛療法は、身体と対話するようなやさしい施術で、あなたが本来の元気を取り戻すお手伝いをいたします。

医学的注意事項(免責事項)
当院で提供している「自律神経無痛療法」は、医療行為ではなく、あくまで民間療法・代替療法に基づく施術です。医師による診断・治療が必要とされる症状や疾患に関しては、まずは医療機関の受診をお願いいたします。
当院の施術は医療行為の代替を目的とするものではなく、身体の自然な回復力を高め、健康維持や不調の軽減をサポートするためのものです。
【参考】 なぜ「やさしい刺激」がからだを変えるのか?
アルント・シュルツの刺激法則とは
私たち心整体いきいき堂が行っている「自律神経無痛療法」では、強く押したり揉んだりといった刺激は一切行いません。その理由は、ただ単に「痛みを与えたくない」からではありません。実は、人間の身体は「やさしい刺激」にこそ、最も良く反応するという科学的な法則があるのです。
この法則は、19世紀のドイツの薬理学者アルントとシュルツによって提唱されたもので、医学・生理学・リハビリの分野でも広く知られており、以下のように説明されます。
アルント・シュルツの刺激法則
〜 刺激の強度と神経や筋の興奮性について述べた法則 〜
この「アルント・シュルツの刺激法則」は、まさに私たちの施術方針と一致しています。
強い刺激は、筋肉や神経を一時的に麻痺させたり、過剰な防御反応を引き起こしてしまうことがあります。一方、穏やかで心地よい刺激は、身体の緊張を自然にゆるめ、本来の回復力を引き出すのです。
この科学的な原則を土台に、「身体に優しく、効果は深く」を実現しているのが、当院の無痛療法です。
ご相談・ご予約方法
自律神経無痛療法 施術料金
🌿施術メニューと料金のご案内
お悩みや目的に合わせて、3つのコースをご用意しています。
どのコースがご自身に合うか迷われる場合は、お気軽にご相談ください。
◾️肩こり改善お試しコース(約20分)
2,980円(税込)
初めての方限定の体験コース。
肩こりや肩甲骨まわりの張りを無痛で軽やかな感覚を体験いただけます。
◾️慢性不調改善コース(約60分)
6,500円(税込)
慢性頭痛・めまい・自律神経の不調・腰痛など慢性不調に対応する基本コース(自律神経無痛療法を施術します)です。
◾️心と身体の不調改善コース(約90分)
12,000円(税込)
自律神経無痛療法+カウンセリング付きコースになります。あなたがどんな性格のタイプか… など、自分を知り、思考のクセを見直すことで身体と心を同時に整えていきます。
お支払い方法
- 現金
- PayPay
クレジットカードでのお支払いはできませんのでご了承ください