【第3弾】脳はなぜ“勝手に緊張”してしまうのか?|慢性不調を生む「反応パターン」の正体
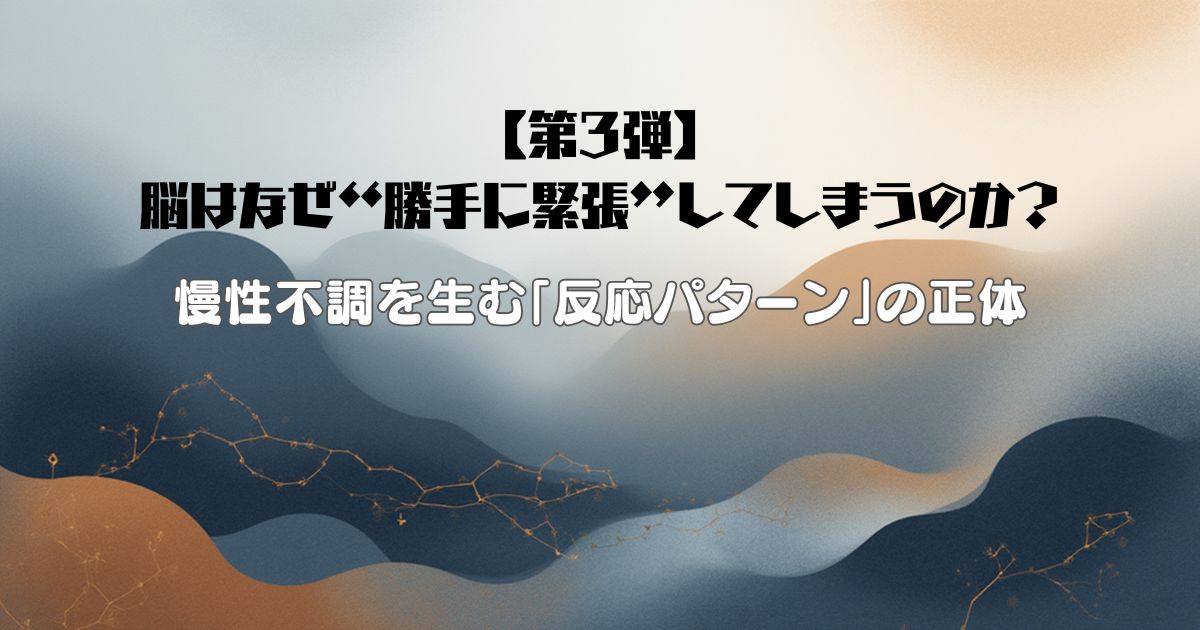
【第3弾】脳はなぜ“勝手に緊張”してしまうのか?
──慢性不調をつくる「反応パターン」の正体
私たちが不安になるとき、
緊張して苦しくなるとき、
焦りが止まらないとき——
じつは、
脳は勝手に「防御反応」を起こしているだけなのです。
これは意思の問題ではありません。
「気の持ちよう」でもありません。
脳が“過去の経験”をもとに
自動で判断し、反応しているだけです。
この脳の自動反応を、
10週間セッション(10WS)では 「脳の反応パターン」 と呼んでいます。
今日はその仕組みを、わかりやすくお伝えします。
■ 脳は「現実」ではなく「記憶」で判断する
脳が最も優先するのは
あなたを危険から守ることです。
しかし脳は
“過去に怖かったこと”
“怒られた経験”
“つらかった出来事”
を全部ストックしています。
そして新しい出来事が起こったとき、
脳はこう判断します。
「これはあの時に似ている…危険かも!」
↓
「緊張して備えろ!」
↓
身体が固くなる、息が浅くなる、不安になる
これが 脳の反応パターン(自動処理) です。
■ 緊張しやすい人には理由がある
緊張しやすい人、不安になりやすい人には共通点があります。
それは、
脳が「安心」を感じた時間が少なかった ということです。
・我慢して生きてきた
・人に合わせてきた
・怒られないように気を張ってきた
・「ちゃんとしなきゃ」と思い続けてきた
こうした積み重ねで、
脳は“警戒モード”を学習します。
結果として、
脳:いつも危険に備える状態
身体:常に緊張する状態
が続いてしまうのです。
これは欠点ではなく、
「そうせざるを得なかった」だけです。
■ 身体の不調は「脳の勘違い」から始まる
多くの慢性不調は、
実は 身体ではなく脳の誤作動 から始まります。
脳が「危険だ」と判断すると、
筋肉を固くし、
呼吸を浅くし、
心臓をドキドキさせ、
血流を変え、
内臓の働きを抑え…
身体はすべて脳の反応に従います。
つまり——
身体の不調の多くは
“脳の緊張パターン”の副産物なのです。
■ 反応パターンは“気づく”ことで弱まっていく
脳の反応パターンは、
無意識で動いているので自分では分かりません。
だからまず必要なのは、
自分の反応を客観的に知ることです。
10WSでは、
「どの場面で緊張するのか?」
「どんな言葉に反応するのか?」
「どんな状況で不安が強くなるのか?」
を一緒に整理していきます。
そうすると脳がこう感じ始めます。
「あれ?危険じゃないかもしれない」
↓
「ちょっと力を抜いても大丈夫かも」
これが起こると、
身体が勝手にゆるみ始めます。
■ 多くの方が体験する“ゆるみ”の瞬間
・呼吸が深くなる
・肩の力がストンと落ちる
・胸のつかえが消える
・不安が減っていく
・「あれ?なんか平気になってる…」と感じる
こうした変化は、
脳の反応パターンが弱まってきたサインです。
■ 次回は第4弾:本来の声が戻ってくるタイミング
次回は、
10WSの山場である Week4〜6の変化 に触れていきます。
・「本当の声」が聞こえ始める
・我慢の人生からの解放
・緊張の背景にある“前提”の崩れ
・生き方のシフト
ここが、多くの方が涙する大きなポイントです。
どうぞ楽しみにしていてください。
